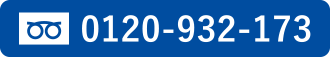\人を雇う/
フリーランスが人(アルバイト)を雇おうと思ったらどういう手続きを踏んだらいいの?
【①提出書類2枚】
給与支払い始める届出を管轄の税務署に提出します。
①給与支払事務所等の開設届出書
従業員を初めて雇用した日から1ヶ月以内に提出。
②源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員が10人未満である場合、毎月の納付を半年に一度の頻度にまとめることができる。
バイト代一人に月88,000円を超えそうなら
②も併せて出しておきましょう!
【②労働条件通知書の作成】
雇用主からアルバイトにどういった条件で雇うかを伝えるための書類です。
明記必須事項もありますので、
『労働条件通知書 テンプレ』
で調べて、自分で作成しましょう!
【➂法定4帳簿の作成】
労働基準法に基づき、以下の4つの書類整備をしないといけません。
・労働者名簿
必須記載項目は氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務、雇入年月日、退職年月日など
・賃金台帳
必須記載項目は、氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数(深夜.休日.残業時間を含む)、基本給与及び手当額、賃金控除額など
・出勤簿
記載項目は、氏名、出勤日、出勤日毎の始業.終業時間、休憩時間、残業時間など
・年次有給休暇取得管理簿
※年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者を雇う人は作成。
必須記載項目は取得日、付与日、日数
【④労災加入手続き(詳細)】
・労働保険成立届
保険関係が成立した日の翌日から10日以内に、管轄内の労働基準監督署に提出。
・労働保険概算保険料申告書
保険関係が成立した日の翌日から50日以内に、日本銀行または管轄内の労働基準監督署、都道府県労働局のいずれかに提出。
※保険関係が成立した日:事業開始の日または(労働者を使用するなど)
その事業が適用事業に該当するに至った日に自動的に成立します。
【➄雇用保険加入の確認(詳細)】
▶労働時間が週20時間以上、1ヵ月以上働く見込みアリのアルバイトを雇う場合は、雇用保険加入となり、以下の書類を提出します。
・雇用保険適用事業所設置届
設置日の翌日から10日以内に管轄内の公共職業安定所(ハローワーク)に提出。
・雇用保険被保険者資格取得届
資格取得の事実があった日から翌月10日までに管轄内の公共職業安定所(ハローワーク)に提出届。
【⑥源泉徴収・年末調整】
アルバイトを雇う場合、アルバイト給与から所得税を引いて
その所得税を給与を支払った月の翌月10日までに税務署へ納付します。
※本投稿の「①提出書類2枚」ー②の書類を提出することで半年に1回納付できます!
それに加え・・・
・年末調整
所得税を徴収しすぎた場合は還付、
不足している場合は追加徴収を行う必要があります。
アルバイトを雇うとなると
いろいろ手続きが必要なんですね🤔💭