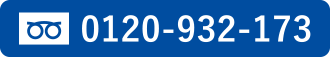★インボイス制度〇〇の人は影響大⁉★
\インボイス制度の影響ある人ない人/
全ての事業主が
インボイス制度の影響を
受けるわけではありません❕
そこで今日は、
インボイス制度の影響を
受けやすい人・受けにくい人
はどんな人なのか解説していきます🙌
【影響の大きい人は?】
▶売上が1000万円以下の
個人事業主・フリーランスで
仕事の取引相手が
主に企業・事業者の場合!
この場合、相手から適格請求書の
発行を求められるケースが
多くなることが予想される。
例)フリーのデザイナーやプログラマー、
個人タクシー、一人親方など。
【逆に影響のない人】
①もともと課税事業者
▶インボイス制度は
売上が1000万円以下の
消費税免税事業者に
大きく影響を与える制度です!
元々売り上げが1000万円を超えていて
消費税を納税している人には
影響は少ない場合が多い。
ただし、免税事業者と取引をしている
場合は消費税の負担額が増えるかも・・・💦
②お客さんが消費者
▶「お客さんが事業者じゃない」
という人は
インボイス制度の影響を受けにくい!
事業者として消費者を納税することがない消費者は、
もちろん適格請求書(インボイス)も必要ありません。
例)美容院などの美容系、
タピオカドリンクなどの若い子が
ターゲットのお店、子供用の塾など。
➂お客さんが簡易課税事業者
▶簡易課税とは
納税する消費税額を
売上の消費税-(売上の消費税×みなし仕入率)
で算出する方法!!
❌実際に発生した消費税を計算して納める
⭕売上の一定率で消費税を算出する
というやり方!
▶簡易課税を選択した事業者の
消費税納税額は、
売上額に依存する!!
つまり、適格請求書があっても
なくても納税額は変わらない!!
なので、お客さんが簡易課税事業者の場合、
適格請求書を発行する必要なし。
なかなか見分けが難しいけど…
この場合も制度の影響は少ないです。
自分にはどういう影響が出るだろう?
対策はどうすればいいだろう?
と一度考えてみましょう🤔💭