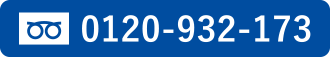★生命保険 税金の話★
\必要なとこだけまとめときました!/
【意外と知らない、保険まわりの税金】
まず前提として・・・
世の中にはいろいろな税金があり
特にお金が動く時に発生するものが多いです。
・資産を得る時 →所得税・住民税
・資産を使う時 →消費税
・資産の所有権が移る時(死亡時) →相続税
・資産の所有権が移る時(生存時) →贈与税
このうち、保険に入る人が知っておきたい
税金について解説していきます!
誰がどういう状況で受け取るかで税金が変わります!
【生命保険(死亡保障)の場合】(相続税・受取人の所得税)
*一時金で受け取る場合
配偶者であれば1億6千万円もしくは、相続財産の半分いずれか大きい方まで非課税。
配偶者以外は、3000万+法定相続人の数×600万
死亡保険金や死亡退職金がある場合は、
上記に加え、法廷相続人の人数×500万まで非課税。
→一般家庭で掛ける保険金額なら、概ね『非課税』
*年金で受け取る場合 ←収入保障保険もこれ
年金受け取りをした場合に支払総額4800万、
一括受け取りだと4500万になる保険の場合
4500万が相続税の対象(一時金で受け取る場合と同じ)
年金受取により増えた300万が、受取人の毎年の所得税。
→毎月必要な生活費などは年金受取で計画的に使うのも◎
【3大疾病、高度障害、医療の場合】
3大疾病や高度障害、医療保険など
保険を掛けられている本人が大変な時に受け取るお金は
いくら受け取っても、全額非課税となります。
※契約者と被保険者が別の場合、被保険者が受取人になります。
🏥3大疾病保険金500万円 非課税
♿高度障害保険金3000万円 非課税
→生命保険の場合、一度保険が支払われると
契約が消滅するのでその後の保険料負担もありません。
【貯蓄型保険の増えたお金を現金で受け取る場合】(総合課税と分離課税の違い)
資産形成により増えたお金を受け取る場合
NISAなど一部の仕組みを除いて
所得税の対象になる可能性がありますが、
課税方法は2種類あり、保険は『総合課税』になる。
*総合課税
その年の他の所得と合算(総合)して課税。
※年間での総所得が高いほど税率が高い
*分離課税
その他の所得と関係なく(分離して)課税
※一律で利益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
→どちらが損得という話より、まず違いの理解が大事。
→総合課税は年間所得なので利益を複数年に分けると◎
【貯蓄型保険の増えたお金を現金で受け取る場合】(所得税・住民税)
*一時金で受け取る場合(解約・減額)は、一時所得。
一時所得の金額=
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)
一時所得金額の1/2が所得に合算され、課税対象になる。
→必要な時に必要な分を、年々減額しながら使うのが◎
→給与所得が高い現役の時より、退職後に取り崩すと◎
→受け取り方さえ間違えなければ、メリットがある
→一年のうちに利益取りすぎ注意(社会保険料や税率に影響)
*年金で受け取る場合は、雑所得
雑所得の金額=
総収入金額-収入を得るために支出した金額
→公的な老齢年金も雑所得にあたる
イレギュラーな契約形態の注意点
【契約者と被保険者が違う場合・契約者と口座名義人が違う場合】
ここまでの話は契約者と被保険者が同じで
契約者が自分自身で保険料を払っている前提でした。
*契約者と被保険者が違う場合
たとえば被保険者である妻が亡くなった事で
契約者である夫が死亡保険金を受け取る場合は、
相続税ではなく契約者の所得税になります。
(=相続税の1億6千万まで非課税の特典が使えない)
*契約者と口座名義人が違う場合
夫婦間で通常必要な程度の金額の保険なら
あまり気にしなくていいと思うのですが、
親子間で贈与などの目的で大きな金額を動かす場合、
特に親の口座から直接子供名義の保険に大金を払うのは要注意。
→イレギュラー契約は担当者に確認しながらすすめましょう
【税金関係で一番大事なことは・・・】
税金のルールってどれくらいの頻度で見直すか
知っていますか?実は・・・
1年に1回、毎年見直ししてるんです。
税負担の公平性を保つために、毎年改正案を出して
少しずつ変えていってるんだって。
だから、ここで税金の話をするのは
加入時に気を付けて欲しいからじゃない・・・。
むしろ加入時はほぼ気にしなくていい。
ただし・・・将来、保険を使うときは
お金を動かす前にはそのときの税金のルールを
よく確認してくださいね⚠