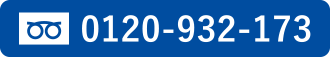法人保険のメリットとデメリットを実例で解説
中小企業にとって、法人保険は
会社を守るための大切な仕組みです。
ただし、メリットもあればデメリットもあります。
ここでは、できるだけわかりやすく、
実際の事例も交えながらまとめました。
⸻
1. 法人保険とは?
法人が契約者となり、社長や役員、
目的はシンプルで、
「社長に万が一のことがあっても、
⸻
2. 法人保険のメリット
① 社長・キーパーソンの“就業不能リスク”に備えられる
中小企業では、社長が倒れると
給与支払い、取引先対応、銀行対応などがすべて止まります。
法人保険があることで、
その期間の運転資金を確保できます。
〈実例〉
ある製造業の社長が病気で入院した際、
法人保険からの2,000万円が資金として役立ち、
給与・外注費を遅れなく支払うことができました。
⸻
② 事業承継の資金を準備できる(退職金・自社株買取など)
事業承継では、
退職金や自社株の買取資金が必要です。
法人保険を使うことで、
その準備を計画的に進められます。
〈実例〉
ある企業は勇退退職金9,000万円を準備するため、
法人保険を活用しながら着実に積み立てを行いました。
⸻
③ 銀行や取引先からの信用が高まる
法人保険に加入している会社は、
• リスク管理ができている
• 社長不在の時でも資金が確保される
• 経営が安定している
と評価されやすくなります。
〈実例〉
法人保険でリスク対策を整えた会社は、
銀行からの融資枠が拡大しました。
⸻
3. 法人保険のデメリット
① 途中解約すると損をする場合がある
返戻金が増えるには時間がかかるため、
短期で解約すると損をする可能性があります。
⸻
② 資産運用ではない(あくまで保障が中心)
「増える保険」というより、
法人保険は**“会社を守るための備え”**です。
⸻
③ 保険料が高くなる場合がある
法人保険は保険料が大きくなることがあります。
会社のキャッシュフローに合った設計が大切です。
⸻
4. 法人保険の正しい使い方
法人保険が本当に役立つのは次の場面です。
• 社長が倒れたときに会社を止めたくない
• 事業承継のための資金を準備したい
• 会社の信用を高めたい
目的がはっきりしていると、
法人保険は大きな力になります。
⸻
5. まとめ
法人保険は、
会社の未来と、そこにいる人の人生を守るための仕組みです。
メリットとデメリットを理解したうえで、
会社の状況に合った保険を選ぶことが大切です。
必要であれば、
現在の保障内容の見直しや、
事業承継・リスク対策のご相談も可能です。
いつでもお気軽にお声かけください。
⸻
経営者向けの情報共有チャット「エミシェア」を運営しています!
〝未来は、待つな。創れ。〟
興味のある方は、こちらからご参加ください。
▶▶ 参加はこちら
https://line.me/ti/g2/