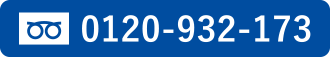社員が安心して働ける会社に共通する “保険の仕組み”とは?
「この会社なら、長く働けそうだ」
社員がそう感じる会社には、
共通して“見えない安心の仕組み”があります。
それは、
福利厚生の派手さでも、給与の高さだけでもありません。
万が一のときに、会社がどうなるか。
社員と家族がどう守られるか。
そこまで考えている会社かどうかです。
本記事では、
社員が安心して働ける会社に共通する“保険の仕組み”を、
実務視点で解説します。
⸻
なぜ今「社員の安心」が経営課題なのか
近年、経営者からこんな相談が増えています。
• 社員の定着率が下がっている
• 若手が将来に不安を感じている
• 幹部候補が育たない
• 「会社の将来」が社員に伝わっていない
原因の多くは、
“会社が有事に耐えられる構造になっていない”ことです。
社員は意外なほど、
会社の不安定さを敏感に感じ取ります。
⸻
社員が不安に感じている「本当のポイント」
社員が口にしない本音は、ここです。
• 社長に何かあったら、この会社は大丈夫だろうか
• 給与や雇用は守られるのか
• 家族に迷惑がかからないか
• 会社は続くのか
これらはすべて、
経営リスクと直結しています。
⸻
安心して働ける会社に共通する3つの保険の仕組み
① 社長不在でも会社が止まらない仕組み
社員の安心は、
「社長が倒れても会社が回るかどうか」にかかっています。
そのために必要なのが、
• 社長の死亡・就業不能時の資金確保
• 借入返済・運転資金の確保
• 急な経営判断を支える資金余力
これを保険で準備している会社は、
有事でも社員の雇用を守れます。
⸻
② 社員と家族を守る“福利厚生としての保険”
社員が安心する会社は、
「働く本人」だけでなく
家族の安心まで視野に入れています。
例えば、
• 業務中・業務外の万が一への備え
• 病気やケガで働けなくなった場合の保障
• 遺族への備え
これらを会社の仕組みとして用意しているかどうかが、
信頼の差になります。
⸻
③ 保険を“節税”ではなく“経営継続”で使っている
安心できる会社に共通しているのは、
保険の目的が明確なことです。
❌ 節税のため
❌ 勧められたから
❌ なんとなく
ではありません。
☑ 社長不在対策
☑ 経営継続
☑ 雇用維持
☑ 社員と家族の安心
目的が「経営」に向いている保険設計こそ、
社員の安心につながります。
⸻
「保険がある会社」と「ない会社」の決定的な差
万が一が起きたとき、
• 保険がある会社
→ 会社は続く。社員は守られる。
• 保険がない会社
→ 判断が遅れ、資金繰りが悪化し、
最悪の場合、雇用が守れない。
社員は、
この“差”を本能的に感じています。
⸻
エミシェアが大切にしている考え方
エミシェアでは、
保険をこう定義しています。
「保険=社長不在でも会社が止まらない仕組み」
• 社員が安心して働ける
• 家族が安心して送り出せる
• 経営者が覚悟を持てる
そのための経営インフラです。
⸻
まとめ|社員の安心は「仕組み」でつくれる
社員が安心して働ける会社には、
共通点があります。
• 有事を想定している
• 感情ではなく構造で守っている
• 保険を“経営の道具”として使っている
安心は、
気合や想いだけでは生まれません。
仕組みで整えるものです。
⸻
社員と家族の安心を、本気で考えたい経営者へ
エミシェアでは、
法人保険を入口に、
• 社長不在リスク
• 就業不能リスク
• 経営継続
• 雇用維持
を実務ベースで整理しています。
「うちは大丈夫か?」
そう思った今が、
整えどきかもしれません。
⸻
経営者向けの情報共有チャット「エミシェア」を運営しています!
〝未来は、待つな。創れ。〟
興味のある方は、こちらからご参加ください。
▶▶ 参加はこちら
https://line.me/ti/g2/